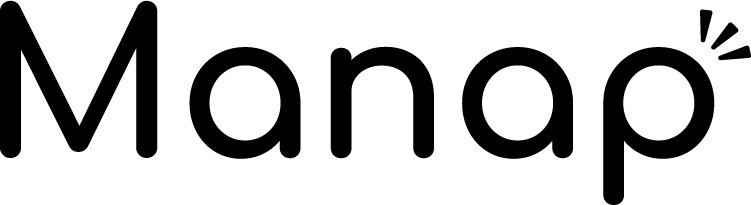毎日の食事は、健康な体を作るために欠かせないものです。
それは大人も子供も同じこと。
食育とは、食事を通して感謝の心を忘れないようにすることであったり、マナーを守ったりと学ぶことがたくさんあります。
そんな食育に関する、食育アドバイザーという資格が話題になっているのをご存知でしょうか?
そこで今回の記事では、食育アドバイザーの資格について、分かりやすく解説していきます。
食育アドバイザーとは?

| スクール名 | 金額(税込) | 学習期間 |
|---|---|---|
| 資格のキャリカレ | 28,600円 | 3ヶ月 |

食育アドバイザーとは正しい知識を備えて健全な食生活を実践できるスペシャリストです。
資格を取得することで、日々の食生活を豊かなものにしてくれるでしょう。
食生活の影響
ファストフードや冷凍食品、スナック菓子など手軽に食べられて美味しい食べ物はたくさんあります。
日本人は食べる物の選択肢がたくさんあり、ついつい手軽に食べられる物を口にしている人も多いです。
しかし、食べるものが発育中の子どもに与える影響は大きいです。
それらが原因で子どもの中には、アトピーやアレルギーを発症することもあります。
食育の大切さ
食育とは、安全な食材の見分け方から最適な栄養バランスを考え、食の選択をして健全な食生活を送ることのできる人間を育てることです。
2005年に制定された食育基本法においては、食育は教育の基礎となるべきものだとされていて、国を挙げて食育の推進を行なっています。
また、食育は子ども達だけでなく、成人病の予防や高齢者の病気の予防など大人にも必要とされています。

家庭で食育を実践することから地域や教育現場、医療現場など食育が必要とされる場は幅広いです。
食育アドバイザーの重要性
食育アドバイザーは、栄養学や食育の正しい知識を身につけたスペシャリストです。
安くて美味しい食べ物はたくさん溢れていますが、その中から安全なものを選択する知識、栄養バランスと健康を考えた献立を実践する力を身につけます。
家庭で実践することはもちろん、食の大切さを多くの人に伝えて、正しい食生活を指導することが可能です。

近年では、食育アドバイザーは食育の普及と推進を担う力として期待されています。
このように、食育アドバイザーは現代社会の食の乱れを改善する役割として期待されているのです。
食育アドバイザーの口コミ

久々の学習で不安の中、受講しましたが実際は内容がぎゅっと分かりやすくまとまっていてよかったです。
家事育児、仕事の合間に少しづつ進められました。
自分が興味があって始めた学習なので楽しく受講できたので満足です。

子供がいると時間がない、スケジュールが組みにくいなどの理由でやりたいことがなかなかできず、諦めてしまうことが多々ありました。
しかし、この講座は在宅でできるだけでなく、スマホで学習動画が見れたり、添削問題を解くことができたりと子育て主婦にはありがたい学習サポートで感動!
スキマ時間を利用して無理なくマイペースに学べ、諦めなくて本当に良かったと思っています!
寝かしつけたけど別室に行くと起きてしまう…なんて時は、イヤホンをして動画で学習!抱っこしたまま寝てしまったときだって大丈夫!
もし、子供を理由に悩んでいるのであればぜひチャレンジしてほしいです☆

テキストも要点をまとめてるので分厚くないし、動画も数分でわけられているので少しずつ進めやすい。
テストも同じく量が多すぎないのがやりやすかった。ただ個人的にはテストをすることで理解しているか確認ができたので、本番のテストと別に練習問題をはさんであった方が理解を深めやすかったかもと思う。
食育インストラクターとの違いは?

| 講座名 | 金額 (税込) |
学習期間 |
|---|---|---|
| 食育インストラクター | 39,900円 | 6ヶ月 |

食育インストラクターは、特定非営利活動法人NPO日本食育インストラクター協会が認定しています。
NPO日本食育インストラクター協会は、食育に関する理解や実践レベルなどに応じてインストラクターの資格を5つの段階に分けています。
5段階とは、1級から4級に「プライマリー」を加えたものです。
例えば、プライマリーを受ける場合、協会が指定する内容の通信講座を修了していることが条件。
規定の試験に合格した人が認定登録される資格です。
公式ページ お申込みをする前に!
>>「食育インストラクター」の通信講座を資料請求する(無料)
食生活アドバイザーとの違いは?

| スクール名 | 金額 (税込) |
学習期間 |
|---|---|---|
| ユーキャン | 36,000円 | 4ヶ月 |
食生活アドバイザーは「一般社団法人 FLAネットワーク協会」が認定機関となります。
食と生活を結びつけ、より健康的な生活を送れるようサポートするのが食生活アドバイザーの目的であり、3級から受けることが可能です。

認定機関の違いが何か影響をもたらすわけではありませんが、資格取得の大前提として覚えておきたい知識でしょう。
公式ページ お申込みをする前に!
>>「食生活アドバイザー」の通信講座を資料請求する(無料)
食育アドバイザーの資格を取得するには?

それでは食育アドバイザーになるには、どうすればいいのでしょうか?
食育アドバイザーの資格とは?
食育アドバイザーの資格は、『一般財団法人日本能力開発推進協会』によって認定されます。
受験資格は特になく、食育に関心がある人なら誰でも挑戦できます。
試験は特定日に行われるものではなく、在宅で試験を受けることができるので受験しやすいです。
試験内容は?
学習範囲は、栄養学の基礎、体の仕組み、正しい食生活を実践する方法、肥満やアレルギーを持つ人への食育指導方法、生活習慣病予防の見地からの食育指導方法などです。

知識や経験がなくても通信講座などの学習でしっかり学べば初心者でも資格取得が可能だと言われています。
他の食に関する資格試験を見てみると、調理師は経験年数や学習期間など受験資格が定められています。
食育アドバイザーの資格は在宅でも取得が可能
管理栄養士などの資格は食の中の特定の分野のプロフェッショナルですが、食育アドバイザーの資格は食に関する幅広い知識を身につけることになるので、活躍できる場も広がりそうです。
また、在宅受験がいつでも可能なことや受験資格がないことからもチャレンジしやすい資格と言えるでしょう。
初心者でも学習期間が比較的短いことなどから、すぐに専門スキルを短期間で身につけたい人にも資格取得が可能です。

食育アドバイザーは、在宅でも資格取得が可能なんですよ!
・食育アドバイザーは民間資格
・試験内容は栄養学の基礎から指導方法まで
・在宅でも資格受験が可能
食育アドバイザーの資格を取得するメリットは?


食育アドバイザーの勉強をして、資格を取得すると様々なメリットがあります。
食に関する正しい知識が得られる
食育アドバイザーは、食の大切さを伝えることができる、食育や栄養学の正しい知識や健康的な食生活を実践する力を持つ専門家です。
また、食育は子どもたちへの教育というイメージがありますが、実際には生活習慣病の予防や高齢者の病気予防、健康的な食生活のサポートにも活かすことができます。
仕事の需要がある
その他にも、幼稚園や学校などの教育現場を始め、飲食店や食品製造や食品販売、福祉や医療の現場などからも必要とされるでしょう。
具体的には、新メニューの開発や販売に役立てワンランク上の仕事を実現できたり、健康管理に役立てたりすることができます。
また、お年寄りや障害のある人が健康的な食事をおいしく食べることができるようにアドバイスをすることも可能です。
なので、福祉施設や高齢者施設、食品販売などで知識を生かすことができるようにもなります。
食品の販売では、「おいしい」と言うだけではなく、どのような観点からおすすめなのか、産地や添加物、安全性や調味料など幅広い視点から詳しく説明をすることができるようになるので、説明に説得力が増し、信頼度が高まり、質の良い仕事につながるというわけです。

総合的な食育の知識を持ち、実践的に活動することができる食育アドバイザーは、今後ますます必要とされるでしょう。
食育アドバイザーの講座カリキュラムは?
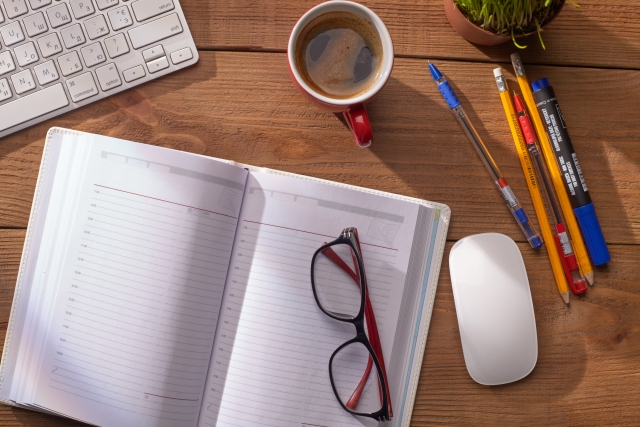

食育アドバイザーの講座ではどのように学習していくのでしょうか?
食育指導について幅広く学ぶ
まずはじめに、食育の目的や食事習慣、マナーや食分野など食に関わる幅広い知識・栄養学やバランスの良い食生活を送るための実践方法を学ぶことができます。
これらの内容を学ぶことで、幅広い世代に栄養バランスの良い食事を提供することができるでしょう。
食品の選び方を学ぶ
次のステップとして、食品添加物や有害物質、遺伝子組み換え食品などが多く含まれている食品の安全な選び方を学んでいきます。
新鮮な食品の選び方など、普段の食生活にすぐに役立ち、子供たちにも伝えたい実践力を身につけていくことも目標です。
食育アドバイザーとしての実践を学ぶ
最後に、食育アドバイザーとして役立つ実践的な活動方法を学びます。
食育の実践方法を参加者に伝えていく食育セミナーや調理体験を通じて職への理解を深めていく料理教室の開催など、多くの食育活動の事例を知ることができるのです。
これで、食育について初めて学ぶという人でも、活動のイメージを持つことができます。

多くの事例の中から、自分が行いたい食育活動を発見することができます。
・食の知識を幅広い範囲で学ぶ
・食品・食材選びを学ぶ
・実践的なことを学ぶ
資料請求ページ お申込みをする前に!
>>「食育アドバイザー」の通信講座を資料請求する(無料)
食育アドバイザーの教材・テキストは?
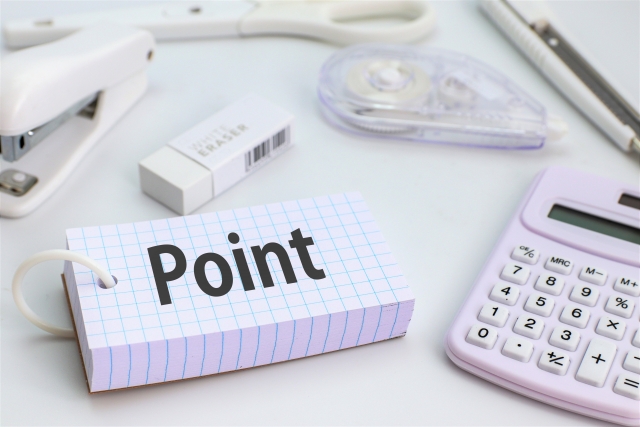
教材・テキストの内容は?

食育アドバイザーの教材・テキストは、子供からお年寄りまで全ての世代に合わせた食の知識を網羅しています。
これにより、それぞれの世代に必要なエネルギー量や栄養バランスが理解できるようになるでしょう。
また、
- 着色料
- 酸化防止剤
- 膨張剤
などの添加物についても学べるので、食品表示の意味や食の安全性の理解を深めることもできます。
そして、食育活動の準備や集客方法の詳しい解説を記載しており、実践的なスキルを身につけることも可能です。
分かりやすい工夫をしてくれている

また、内容面での充実だけでなく、分かりやすいテキストにするために様々な工夫をしています。
まず、難しい専門用語は理解しやすい言葉を用いた文章で解説してくれるので、初学者の人も安心です。
そして専門的な理論も、フルカラーのイラストや図解を使っているので、目で見て理解することができます。
さらに、それぞれの食材に対して、写真を用いての説明や注意点、Q&Aなどを掲載しているので、学習したい内容を的確に学べるでしょう。
他にも、栄養バランスが整った献立を詳しいレシピと写真付きで紹介するなど、分かりにくい食育の情報を日常生活に関連づけて解説しています。
食育アドバイザーの試験内容は?
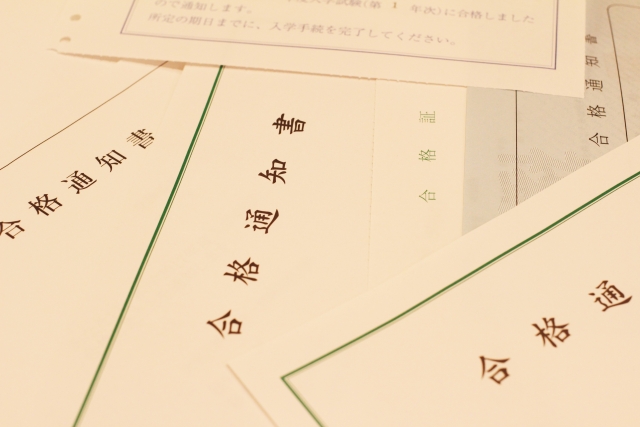
資格試験について
食育アドバイザー資格には、受験資格は存在しません。

学歴や実務経験に関係なく、どのような人でも資格試験を受けることが可能です。
また、一般財団法人日本能力開発推進協会が定めた認定基準を満たした機関の全カリキュラムを修了していれば、何回でも受験することができ、在宅受験も可能となっています。
そして資格試験は、テキストを見ながら受験することができます。
難易度について

食育アドバイザーの資格試験は、70%以上の得点率で合格です。
テキストを見ながらの受験ですので、難易度は高くないイメージがありますが、出題範囲は多岐にわたります。
試験範囲は講座の全範囲となっており、
- 消化吸収の仕組み
- 食品の安全性
- 食物アレルギー
- 食糧問題や環境といった社会問題
- 伝統料理や郷土料理など食事に関する知識
- 医食・薬効・栄養学などの専門的な知識
など、食育活動につなげるための応用力も問われます。
そのため、テキストを見ながらの受験であっても解答を探すのに苦労しますし、テキストの内容を正しく理解しておかないと、応用問題に対応できません。

「テキストを見ながらなので大丈夫」という意識を持たずに、疑問点などをしっかり解消してから受験することが大切です。
食育アドバイザーが活躍できる場は?


食育アドバイザーの資格を取った後、どんな場面で活躍することができるのか?
活躍できる場面を紹介していきます。
家庭での活躍
妊娠期、乳幼児期、学童期、青年期、中年期、老齢期と人間のライフステージに応じても食事の仕方は変わります。
食育アドバイザーは、自分の大切な家族のために知識を活用して、家族の健康を維持する基礎を作ることができます。
社会での活躍
飲食店やレストラン、食品加工会社や食品流通などに携わっている人は、食育の知識を新メニュー開発や販売に役立てることができます。
また、教育現場でも食育アドバイザーの知識は必要とされており、幼稚園や保育園から小中学校まで、学校を挙げて食育が実践されています。

子ども達へ指導する保育士や教員にも食育の知識が必須となりつつあるようです。
そして、医療や福祉の現場でも食育の知識が活かせます。
個人で活躍する人もいる
その他に個人で活躍できる場もたくさんあります。
例えば、食育の大切さ、食への関心をセミナー講師として広めることができます。
子供への指導や、最近は大人でも関心が高い人は多いので、多くの人に食育の知識を広めることができます。
自宅キッチンを利用して料理教室を開いている人もいます。
主婦の中には食への不安を抱えている人も多くいることから、食育アドバイザーの需要は多いようです。

そんな主婦達に向けて、自宅キッチンを開放して食育を実践する献立を教えたり、食育を一緒に学ぶ場にしている人もいます。
・家族の健康を整えられる
・食品・子供関係の職場に重宝される
・個人で料理教室を開ける
食育アドバイザーの受講者の声は?


食育アドバイザーの資格を取得した人に聞いてみた結果がこちらです。
きっかけは家族の健康
実際に食育アドバイザーの資格を取得して活躍している先輩方は、自分の家族の健康を考えて資格取得を目指したことがきっかけだったと語る方が多くいました。
ある方は、「きっかけは自分の家族の健康だったけれど、食育の資格取得で学んだ知識を家庭で実践する中で、家族のアレルギーが解消したり、皮膚炎が治ったりという効果を自分の目で見ることができました。
家族だけでなくより多くの人に健康になってもらいたいと思うようになりました。」と言っていた先輩がいました。

その人は、より多くの人に食育の大切さを知って健康になってもらいたい、という強い思いから、自宅のキッチンを利用して料理教室を開いているようです。
きっかけは子供の健康から
ある方は、自分の子どもの健康のために食育アドバイザーの資格を取得しましたが、地域が主催する料理コンテストで優勝した経験があります。
優勝した時に、食育アドバイザーの資格があることを伝えると、新たな仕事の勧誘を受けたという経験を持つ人もいます。
職場で食に関する質問が多くて
現役の保育士さんの中には、保護者から食生活に関する質問を受けることがあるそうです。
身近なところから
食育アドバイザーの資格を取得した先輩方に共通することは、家庭で食育の知識を活かして実践し、食育の大切さを実感していることです。
食育アドバイザーの資格取得を目指したきっかけは身近なことだったけれど、食育アドバイザーの資格を取得したことで、食に関する幅広い知識に自信を持ち、身近な人たちのアドバイスからさらに広く食育を広めたいと思うようになったと感じる人が多いです。

家族のことがきっかけで食育アドバイザーの資格を取ろうとする人が多いですね。
資料請求ページ お申込みをする前に!
>>「食育アドバイザー」の通信講座を資料請求する(無料)
食育アドバイザーに関連する食育の資格は?
食育インストラクター

| スクール名 | 金額 (税込) |
学習期間 |
|---|---|---|
| がくぶん | 39,900円 | 6ヶ月 |
食育インストラクターの資格の特徴は?

そもそも食育とは、食に関する知識を教育し、広めていくことです。
食育を受けることで、健康に合っている食べ物を選ぶことができるようになり、健全かつ健康な食生活を送ることができるようになります。
また、人が知識を得たり道徳を学んだりする場合、その大前提として健康であることが大切です。
そのため、食育は知育・徳育・体育の基礎となっています。

食育インストラクターとは、食に関しての知識を正しく持ち、広めていき、調理現場でのリーダーシップを取ることができるようになる指導者の資格です。
5つの階級に分かれており、そのうち一番下のプライマリーは在宅で取得することが可能です。
4級からは、会場で試験を受ける必要があります。
食育インストラクターが取得できる通信講座は?
食育インストラクターの通信講座のおすすめは、がくぶんが実施している「食育インストラクター養成講座」です。

推進校の認定があるので、資格取得に直結していることも魅力。
服部幸應氏が監修・指導をしており、栄養に関することはもちろんですが、マナーや文化など、食に関するあらゆることを学ぶことができます。
テキストでの学習や個別の添削を受けることもでき、ドラマ仕立てになっているDVDでわかりやすい学習ができます。
講座を通して学んだ知識をすぐ活かすことができるレシピがついてくるのも嬉しいですね。
公式ページ お申込みをする前に!
>>「食育インストラクター」の通信講座を資料請求する(無料)
食生活アドバイザー

| スクール名 | 金額 (税込) |
学習期間 |
|---|---|---|
| ユーキャン | 36,000円 | 4ヶ月 |
食生活アドバイザーの資格の特徴は?
健康に過ごすためには、食生活の改善はもちろんですが、生活リズムなどもトータルで見直す必要があります。

そのためのアドバイスができるのが食生活アドバイザーです。
ダイエットや肥満など、食に関する悩みがある人に助言をすることもできる資格です。
食を安全や消費など色々な面から見つめ、より健康に過ごすための方法を学習します。
各世代に合った栄養を考えた料理ができるようになるので、仕事はもちろん、実生活で実践できることも多いです。

2級と3級があり、同時受験も可能です。
学習すると、食をもっと楽しめることができるようになります。
※食生活アドバイザーは在宅では資格を取得できません。
食生活アドバイザーを学習できる通信講座は?

食生活アドバイザーの取得には、ユーキャンの通信講座がおすすめです。
初心者でもわかりやすいと評判のメインテキストは2冊で完結するようになっており、4ヶ月で2級・3級の同時受験が可能です。
ちょっとしたスキマ時間を利用して勉強できるような副教材や、講師に分からないところを質問できるサービス、パソコン・スマホでできるWebテストなど、学習を続けやすい工夫が満載です。
4ヶ月でできなくても、12ヶ月はサービスを受けられるので、自分のペースで進めることができるのも魅力です。
公式ページ お申込みをする前に!
>>「食生活アドバイザー」の通信講座を資料請求する(無料)
食育メニュープランナー
| スクール名 | 金額 (税込) |
学習期間 |
|---|---|---|
| たのまな | 22,000円 | 6ヶ月 |
食育メニュープランナーの資格の特徴は?
子どもたちへの食育はもちろんですが、高齢化社会となっている現在、
- 生活習慣病
- メタボリックシンドロームのための対策
- アンチエイジング・美容
などの分野でも、改善の第一歩となるのが食です。

そのため、確実な知識がある食のスペシャリストが必要となっています。
それが食育メニュープランナーです。
食育メニュープランナーが取得できる通信講座は?
食育メニュープランナーの資格取得におすすめなのは、ヒューマンアカデミーのたのまな講座です。

この講座では、栄養学や食文化はもちろんですが、調理法や食育メニューの勉強まで幅広い食の学習をすることが可能です。
プロの知識・技術を身に着けることができるので、管理栄養士・調理師などの国家資格を持つ人のスキルアップにも繋がりますし、普段の生活の食をもっとよくしたいと考えている人にもおすすめの講座です。
公式ページ お申込みをする前に!
>>「食育メニュープランナー」の通信講座を資料請求する(無料)
まずは資料請求から!
資格講座の資料を取り寄せてみませんか?
資格・通信講座のサイトから資料を取り寄せることが可能です。
実際に合うか合わないかを確認する方法として、それぞれの講座を資料請求して比較することをオススメしています。

講座を申し込む前に、まずは自分に合うかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?
資料請求ページ お申込みをする前に!
>>「食育」に関する通信講座を一括で資料請求する(無料)